TOPICS
ISHIN No.103
DXで見えてきた地域社会の近未来
国や経済界、産業界などあらゆる分野でDX化が進んでいる。
医療分野ではマイナンバーカードと健康保険証の一体化をはじめ、地域はもちろん全国どこにいても同じ医療情報が閲覧できて、遠隔診療も可能になっている。
金融や産業界では、スマートフォンやカードによる決済、地域通貨による商品決済なども広がってきた。
DX化の進展で、私たちの生活はこの先どう変わるのか?
医療、金融、産業界から3人の有力者に語り合っていただいた。
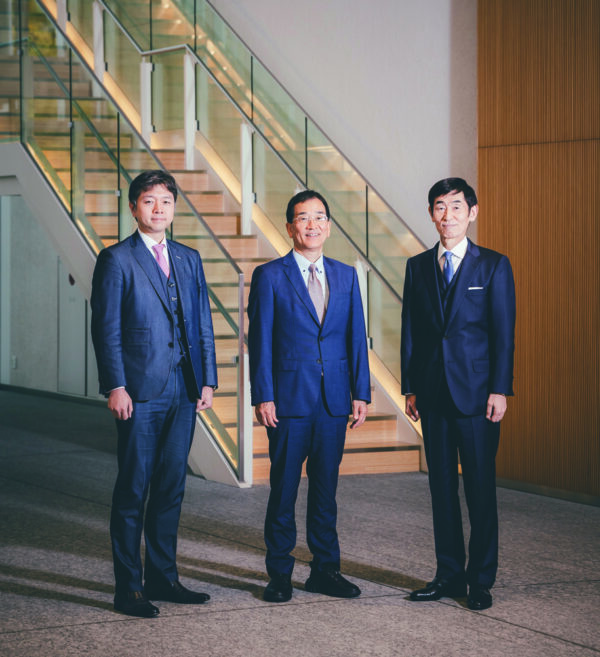
INDEX
電子マネーと現金が共存する
金子 今から7年ほど前、中国の深圳で国際学会があったときにご飯を食べに行こうと近くのお店に入ったら、現金は使えない、クレジットカードもNGで、メニューを頼むのも会計も「QRコード」しか使えませんでした。今なら日本でもその手の店は珍しくないですが、7年前の中国でそうなっていることに驚きました。たしかに人手は少なくてすむし、注文も会計も楽です。システムは全部どこかでつながって処理されていると後から聞いて、中国はずいぶん進んでいると感じました。私自身は新しいことが好きなのでスマホで電子決済などが普通にできるのは歓迎ですが、日本全体を見渡せばそんな人ばかりではありません。若い人はどんどんスマホやパソコンを使いこなせても、うまく使えない人や高齢者はどうなるのだろうと考えてしまいます。それと能登半島地震のときに感じたのですが、やはり現金も必要ではないかと。キャッシュレスが進んで、人手不足の解消や作業の効率化、生産性を上げるためにデジタル技術が必要なのはわかりますが、私たちの生活が今後どういうふうに変わっていくのか非常に気になります。
三谷 現金が必要な場面はまだあるように思います。例えば慶弔とか、神社の賽銭とか。最近は賽銭を電子決済する神社もあるようですが、現金が持っている文化的な意味合いのようなものは今後も尊重されていくのではないでしょうか。そういう場面を残しつつ、一方で最大限効率化していってほしいというのが、一般的な感覚のような気がします。私は、現金を全て電子マネーにしていくのはある上限までで、どちらかというと現金と電子マネーが共存していくのではないかと思っています。デジタルでどんどん効率化を進めるところと、互換性をどういうふうに維持していくかは今後も議論の対象になると思います。
杖村 現金は今後も無くならないですし、無くす必要もないと感じています。ただ流通量は限りなく減ってくると思います。一方で、デジタルに対する恐怖心とか、不安を感じている人は少なくないと思います。デジタル化による犯罪なども増えている中で私たちが取り組むべきは、スマホを使うのが苦手な人に対して、使いこなしたい意向があればヒューマンタッチにリアルで対話をしながらお伝えすることです。各支店で「デジタル教室」を開いていて、この2年ですでに1万回を超えています。われわれとしては10万回くらい続ける気持ちで、電話やHPから予約いただければきちんと対応するようにしています。
システム同士の連携が進む
金子 このひと月ほどの間にヨーロッパとアメリカに行ってきたのですが、そこで感じたのは、ヨーロッパはあまりチップがないので電子マネーでもいいのですが、アメリカはまだチップがあるので現金を持っていかないと何かの時に困ります。そのアメリカもお店の支払いには15%、18%、20%とチップボタンがついていて、これが多くなると「この先、(現金決済も)どうなるかわからない」と感じました。
杖村 日本国内はキャッシュレスと現金が両立すると思いますが、一方で、日本は現金が多すぎて国際的な資金洗浄に使われるなど犯罪の温床になっている面も指摘されています。アンチマネーロンダリング、すなわちテロなどの凶悪犯罪への資金供与の防止対策として、日本人自身が意識をして、特に高額な金額のやりとりについてはだんだん少なくしていかないといけないと感じます。同時に、デジタルを推進するにはやはりセキュリティが重要になってきます。私たちとしても、お客さまにデジタル犯罪から身を守る方法などを対面のセミナーなどを通じて、もっと広めていく必要があると思っています。
三谷 銀行でまとまった現金を下ろす時には、窓口で「何に使われるのですか?」と聞かれます(笑)。たしかに多額の現金は振り込め詐欺など犯罪に狙われやすいので、日常的な決済は電子マネーに変わっていく方がいいと思います。電子マネーは単にデジタルで決済できるだけではなくて、後ろでいろんなシステムとつながっています。販売管理システム、在庫管理や生産管理システムなど、システム同士がどんどんつながって一つのデジタルデータとしてトランザクション(情報処理)されていく。それがいろんな形で効率化され労働力不足にうまく対応できるなど、いろんな変化が産業界や小売の世界に起きていると感じます。
預金と連動した日本初の地域通貨
金子 北國銀行さんは「トチツーカ」という地域通貨を発行しておられます。能登半島地震の影響もあってどうなるかと思いましたが、珠洲地区では使われたと聞きました。銀行預金に接続した地域通貨アプリは日本初だとうかがっています。UI(User interface)やUX(User experience)が良くて、2024年のグッドデザイン賞も取られています。非常に使い勝手が良いですが、マイナンバーカードとの接続は高齢者には難しくないですか?
杖村 ご指摘の通りです。2024年の4月から始まったのですが、私たちとすればUI/UXは現場で検証してみないとわからないところもありますので、ご指摘いただいたところは修正して、2025年春ごろには対応できると考えています。珠洲や輪島など能登の皆さんは地震で大変な思いをされたのですが、実は震災前まではVISAデビットカードを使う人の割合は珠洲地区が日本で一番多かったです。それはスマホやカード決済に苦手意識のある人でも、きちんとお伝えすれば皆さんに利用いただけることを示していて、実際にトチツーカを使えば、細かいお金を出すよりいいんじゃないかが実証されていると思います。トチツーカはブロックチェーンを使っているというと「ビットコイン」に代表される暗号資産(仮想通貨)のように変動性の高い投機的な通貨だと思われますが、トチツーカは変動しません。預金をトークン化したものなので、リスクは少ないと思います。
金子 いずれにしても、法定通貨に価格を紐付けし、価値を安定させる預金型のステーブルコインとしては北國銀行さんが日本で最初に提供・運用されたわけで、この分野では日本のリーダー的存在と言ってもいいと思います。
杖村 ステーブルコインの法整備を待って何かやろうとしたら、たまたま私たちが最初になりました。三谷産業さんも今、日本の金融機関向けで一番高いシェアをもっている製品を開発されています。
三谷 私どもが開発した「POWER EGG」という製品を、2011年に北國銀行さんに最初に導入していただき、金融機関でのモデルケースになったと思っています。POWER EGGは、全国の金融機関の業務改革やコスト削減、人手不足解消などを実現する製品で、地方銀行においては62行中24行で導入され、38・7%の高いシェアをいただいております(2024年11月末時点)。最初は自社向けだったものを民間企業向けに製品化し、石川県や北陸の企業にも数多く導入していただきました。北陸においては、他の地域よりも企業のDX化を進める下地になっていると言えると思います。
医療DXのカギを握る生成AI
金子 ところで、国は2030年度をめどに医療情報のDX化を進めています。その核となるのが電子カルテの標準化です。それを「HL7 FHIR」という形式に則って標準化を進めています。しかし、2030年に用意されるのはカルテのなかの3文書6情報に限られ、医師や看護師が最も重視している経過録の標準化は入っていません。最も重要なところの標準化が難しいためにその部分が抜けている状況にある。そこで、三谷さんに「生成AIでできたらいいよね」という話をしたら、もうプロトタイプを作って提案されました。
三谷 ご提案したプロトタイプは、まだ完全ではないんです。私たちの開発スタイルは、すぐに製品化するのではなく、製品に近づけていくプロセスをお客様と一緒にたどる方向に変化してきています。お客様に「私たちはこういうプロトタイプが作れます」と提案をしながら、お客様が「それだったらこういう使い方もできるね」とインスピレーションを広げる。そのような方法に重点を置いています。また、システムを今の業務に合わせるのではなく、現場の業務をシステムに合わせる開発スタイルにシフトしています。
金子 医療DXは、2024年度中にHL7 FHIR形式のアルファ版が公開され、1年かけて作りこんでいく計画です。この計画に抜け落ちている部分を三谷さんが作り上げられるようになったら、売れるかもしれません。科学の進歩は案外そんなところがあって、新しいものがポンとビジネスに結びつくことがあるものです。
杖村 今、お話されているところはとても重要だと思います。デジタルとかソフトウェアの世界は今、大きく変わりつつあって、大手ベンダーでさえ危うい時代になってきています。会社規模が大きくなりすぎて、おっしゃったようなデジタルの開発や運用まで手が回らなくなっている。開発や運用の仕方自体が根本的に変わる時代がきている感じがします。
医療の情報共有と行政の効率化
金子 医療・介護・福祉の現場では、否応なく情報を共有しないといけない時代になってきています。一方で、国の予算の3分の1を社会保障費が占めている現状から、嫌でも行政の効率化を図らないといけない。つまり国は、医療情報がつながって患者さんや家族が質の高い医療を受けられることと、行政が効率化しないと日本がもうもたなくなる状態を同時に解決したい狙いがあります。ただ、国が今進めようとしている医療DXの中で、必ずしも質の高い医療には届かないと私は思っています。もしかすると、医療DXの本質は質の高い医療を目指すというよりも、行政の効率化にあるのではないかと考えています。
三谷 医療の質が上がるとは、どういうロジックになるのでしょうか?
金子 今の医療DXで整備する3文書6情報には、診療所が患者さんを紹介するときの紹介状、病院を退院して、また診療所でみてもらうときのサマリーなどがあります。基本的な情報がみられることや、はじめて診るとき、紹介のときには確かに便利です。しかし、医療の質を上げているかといえば、そうではありません。今はひとりの患者さんを病院、診療所、薬局、介護施設でリアルタイムに同時にみています。例えば、ある病院で患者さんや家族がこの治療を受けた方がいいけど「受けたくない」と言った場合。家族や本人の思い、それを受けた医師の判断といった記録はその日の経過録に書きます。紹介状に書けば良いと思われるかもしれませんが、その都度お金も発生するし、書く形式も違います。しかし、医療の質を上げようとする場合、同時に患者さんをみている他の医師や看護師、薬剤師、介護士はその情報を一番知りたいわけです。その記録は今の医療DXの計画には載りません。CTとか細かい情報も載りません。それを載せようとするとデータ量が半端じゃなくなるので、とんでもないクラウドのサーバーが必要になります。
杖村 ただ、システム的には可能なように思います。クラウドの費用が膨大になると思われるかもしれませんが、今のGoogleフォトなんかは個人の写真データを無料で保存できているわけですから、金子先生がご指摘いただいたような問題は限りなくクリアできるような気がしますけどね。
三谷 そう思います。プラットフォームとして機能させるために、何が必要かもう少しわかればうまく溶け込める可能性はあると思います。人とシステムの間に存在しないといけないものを、今だと生成AIの力をうまく使えばシステムと人とのコミュニケーションや、人と人とのコミュニケーションも「質」が高まる余地が大いにあると思います。
「利他社会」へのトライアル
金子 とはいえ、デジタルで超えられない壁があって、例えば石川県能美市は高齢者でスマホを持っていない人たちにどうやってサービスを提供していくかを実装実験しています。能美市は内閣府のデジタル田園都市構想事業のモデルになっていて、その一環として市内80数か所にある公民館を拠点に物流機能をもたせています。家にインターネット環境がない人やスマホを持っていない高齢者でも、公民館に来てもらって薬や生活用品をもらえるようにする。最終的にはドローン配送や地域通貨、ライドシェアなどにつなげようとしています。キャッシュレスとか高齢者の医療、介護の見守り、さらに物流や車の配送など全部がつながる仕組みで、「スマートインクルーシブシティ」構想として国の助成を受けて進めています。社会保障だけではなく、道路や水道などの社会インフラもその仕組みの中に関わってくると、社会の仕組みもずいぶん変わると思います。社会が変わることで情報を持ち寄って、それを自分のためだけじゃなく、みんなが得をする「利他社会」につながります。いわばそのトライアルが能美市の取り組みといえます。その時に情報のセキュリティや価値が大切になると思っています。
杖村 会社経営とか経済社会を変えていくためにも、非常に重要なポイントだと思います。おっしゃるように情報はものすごく価値があって、それをうまく取得し、加工したり分析することで戦略が変わってきます。戦略が変わればマーケティングや営業も変わりますし、会社の運営自体が大きく変わっていきます。間違いなくそういう時代に来ていますので、そのノウハウをきちんと使いこなすためにも情報を取得して、うまく利用できる体制を整えるのは重要だと思います。
三谷 当社も他分野の事業をいろいろやっていく中で今、セミオープンインベーションを標榜しています。つまり、異分野同士がつながることで、お互い知恵を重ね合わせたりしながらアップデートしていく。今おっしゃったインフラのアップデートもそうですし、科学の発展の中でも異質な変化を起こせる人間にどうやったらなれるか。異分野や異なる考え方、技術、アイディアなどが混じり合い重なり合うような場を作って、次の時代にチャレンジする準備をしているところです。
新しい価値をデザインする
金子 常勤役員の方全員がG検定というAI、ディープラーニングの試験に合格しているのもその象徴的な例ですね?
三谷 そうです。G検定のGはジェネラルのGですが、一般教養としてのAIに対する理解を役員から率先して深めています。現在、三谷産業社員の75%以上がG検定に合格していて、それによってボキャブラリーが変わりました。「AIが魔法のようになんとかしてくれる」と誰も言わなくなりましたし、AIそのものの性質とか、何ができて、何ができないかをわかった上で使いこなせるようになりました。今ある技術をどう使いこなして、新しい価値を作っていくか。価値作りのデザインが次の目標になっています。
杖村 医学の世界は常に進歩していますし、先生方はそのための勉強や研究を怠らないですよね。ビジネスの世界でも、これからはリカレント教育が重要だと思います。常に役員も社員も学び続けなければ、世の中の変化に対応できませんし、会社も成長し続けることができない時代です。三谷さんがおっしゃった社員の75%以上の合格者はすごいですよ。
金子 北國フィナンシャルホールディングスのリカレント教育もなかなかだと思います。先ほど医学の進歩の話がありましたけど、お医者さんは科学が好きな人が多いので、先生方もデジタルやIT、AIのリテラシーを是非あげていただき、異業種との意見交換やコラボレーションにつなげてほしいと願っています。
HISTORY
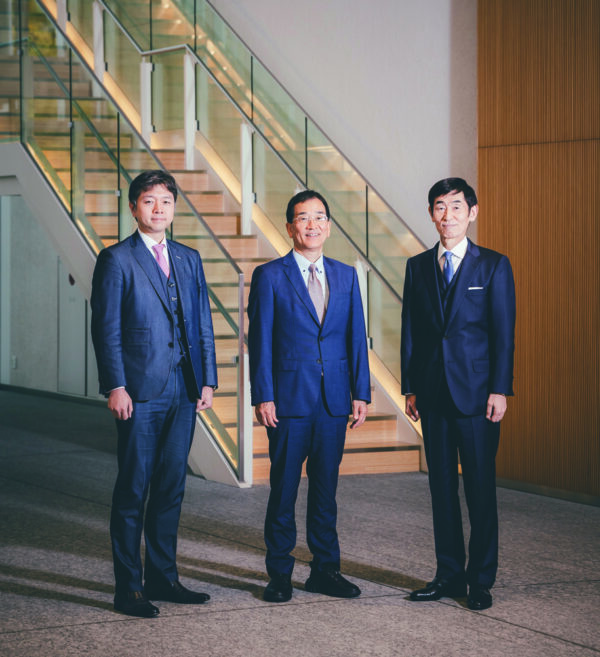
私たちは、あらゆる医療活動の
サポートをします
医心へのご相談やご質問がありましたら
お気軽にお問い合わせください。